「玄孫の手」、400年の歴史に幕 少子・晩婚化余波 京都 これは嘘ニュースです

京都府黄桜町の名産品「玄孫(やしゃご)の手」
背中をかく道具として最もよく知られているのは「孫の手」だが、江戸時代の風俗について記した「嬉遊笑覧」によると、「玄孫の手」は本来「孫の手」「ひ孫の手」の3本セットで販売されており、当時は年齢に合わせてそれぞれ使い分けていたという。
個別に売られるようになった明治期以降、最も数の多い「孫の手」は全国各地で作られてきたが、「玄孫の手」は電球のフィラメントの材料としても知られる黄桜町の竹を使った名産品として、同町でのみ製造が続いていた。昔は「中年になって可愛くも何ともなくなった孫の手では、かゆいところに手が届かない」として、ひ孫や玄孫が生まれるたびに、それぞれ買い替える人も多かったという。
しかし近年、少子化や晩婚化が高齢化を上回るペースで進んだことで、玄孫を持つ高齢者の数が減少。それに伴って、玄孫の手の需要も落ち込み、町工場の数も黄桜町の1件を残すのみとなっていた。「打つ手なし、ですな」。同町でただ一人、玄孫の手を作り続けていた職人の北月木奉さん(88)は、今月末で廃業することを決めた。
「昔と違って『玄孫』という字が読めない人も増えた。『孫の手のパロディグッズ』と言われたこともある。孫の数もひ孫の数も減ってきている今の時代、玄孫という存在自体が日々の生活から遠くなってしまったのだと思う」
同じ理由で「ひ孫の手」もまた存続の危機に瀕している。職人の間からは「もはやこれまで」とあきらめの声も聞かれるが、それでも比較的安定している孫の手の製造に鞍替えしたり、「猫の手」や「猿の手」など派生品の開発に着手したりするなど、手を変え品を変え生き残りに懸命だ。
虚構新聞友の会
本紙友の会へ入会すると、会員専用掲示板に書き込みができます。おすすめリンク
<BOOK>猿の手 (恐怖と怪奇名作集4)
ホワイト氏は、友人のモリス曹長からインドのめずらしいおみやげをもらいました。ミイラの手みたいにひからびた、ただの猿の手ですが、まじないがかけられていて、三つの願いがかなえられる、というのですが―。表題作「猿の手」のほかに、キップリング「獣のしるし」、ディケンズ「信号手」、ジェイムズ「マグナス伯爵」の3編を収録。社主ピックアップ


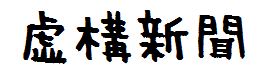


 公式iOSアプリ
公式iOSアプリ 有料メルマガ
有料メルマガ 音声放送
音声放送